📖 今回読んだ範囲(あらすじ・要約)
酒場で知り合ったマルメラードフの身の上話を聞き続けるラスコーリニコフ。
マルメラードフは、せっかく手に入れた職を再び酒で台無しにしてしまったという。
家族──妻のカチェリーナ、娘のソーニャ──は、彼に大きな期待を寄せていた。
それだけに彼の裏切りは深く、彼自身もそのことに心を痛めている。
それでも彼は酒をやめられない。
給料も全て飲み代に消え、挙げ句は売春に落ちた娘にまで金をせびる。
5日ぶりに帰宅するというマルメラードフに、ラスコーリニコフは付き添う。
案の定、怒り狂ったカチェリーナに髪をつかまれ、修羅場が展開される。
怒りの矛先はラスコーリニコフにも向かい、彼は小銭を置いて立ち去る。
自分も極貧の身であるにもかかわらず。
すぐに後悔したが、取りに戻ることはできなかった。
💭 感想
マルメラードフの姿は、“堕ちていく人間”の象徴に見える。
家族を愛しているのに、彼は再び酒に溺れ、家族の信頼を裏切ってしまう。
それでもどこかに後悔があり、悲しみがあり、それを語らずにはいられない。
貧困は、人格すらも浸食していく。
酒場でのマルメラードフの長話は、滑稽であると同時に、痛々しい。
貧乏であるラスコーリニコフも、マルメラードフの境遇に心を動かされ、小銭を置いて帰る。
これは彼の内なる“良心”の表れであると感じた。
しかしその直後、後悔する──この「善」と「迷い」の間で揺れ動く心が、彼という人物の核になっている。
重要な一節の解釈
「だが待てよ、もしおれが間違っているとしたら」と彼はわれともなくふいにこう叫んだ。「もし本当に人間が、人間が全体に、つまり一般人類が卑劣漢でないとしたら、ほかのことはすべて偏見だ、つけ焼き刃の恐怖だ。そして、もういかなる障害もない。それは当然そうあるべきはずだ!……」
この一節は、ラスコーリニコフが自分の考えに迷いを感じた瞬間です。
彼の中には「人間は卑劣な存在であり、理性や善意ではなく利己心や弱さで動くものだ」という前提がある。
しかし、もしそれが誤っていて、「本来、人間は善である」としたら──
今まで積み上げてきた思想や、犯そうとしている計画(まだ具体的には語られていない)が、すべて崩れてしまう。
ここで彼は、思想と本能、冷酷さと良心のはざまでもがいているのです。
「障害はない、それは当然そうあるべきだ!」と強がる一方で、「もしおれが間違っているとしたら…」という疑念を押し殺しきれない。
この一節は、まさにその揺れ動く内面の葛藤を象徴しています。
ラスコーリニコフは他人の痛みを目にして、自分の思想が揺らぎはじめる。
人間は本当に卑劣なのか? それとも善なのか?
彼の思索と迷いは、やがてどんな行動へと結びついていくのか──。
※この投稿は、ドストエフスキーの『罪と罰』をじっくり読みながら、感想や考察を記録していくシリーズの一部です。
これまでの感想一覧はこちら ▶️【シリーズ一覧リンク】
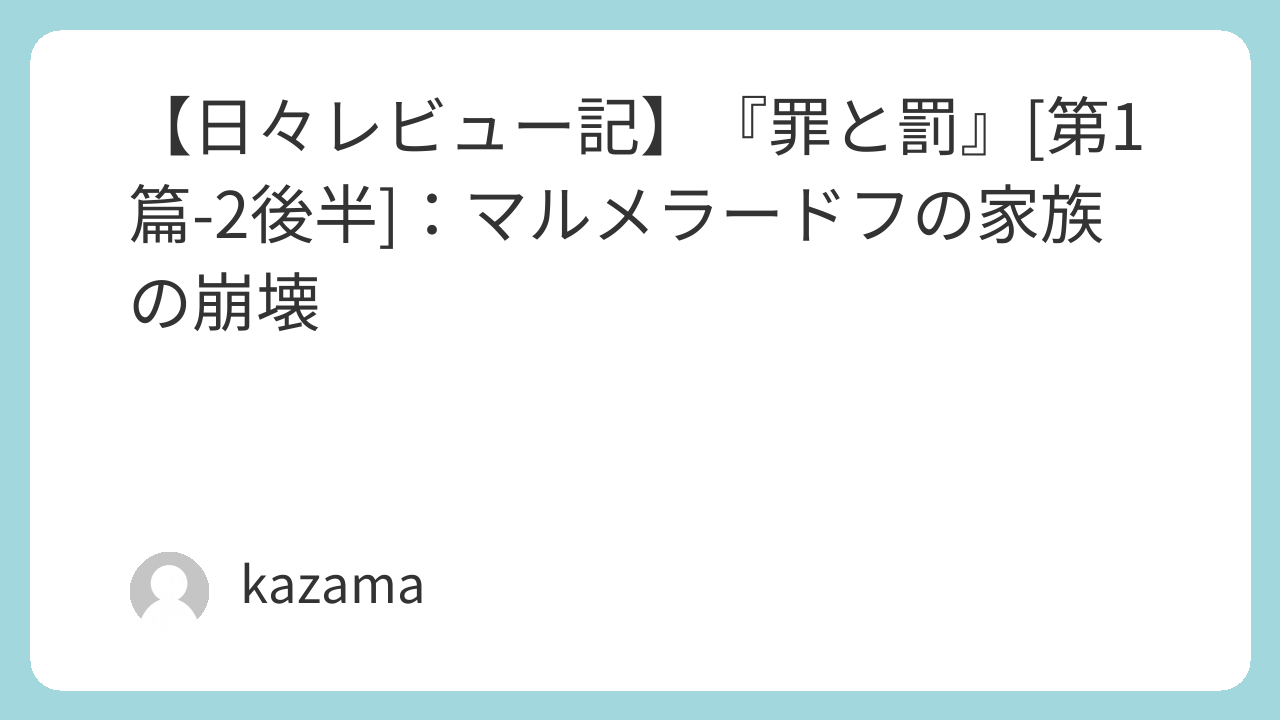


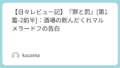
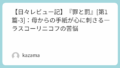
コメント