殺人を犯したラスコーリニコフは、自宅へ戻ると証拠を隠すでもなく、そのまま床に倒れ込むようにして眠ってしまう。不用心な行動に目を覚ました彼は、自分のしたことにようやく気づき、激しい不安に襲われる。
証拠の処理や逃亡よりも、「もうすべてを白状して楽になりたい」という心情が彼を支配する。しかし、そこに突然の“警察からの呼び出し”が届く。ラスコーリニコフは、とうとうバレたのかと青ざめ、絶望のなか警察署へと向かう。
ところが、その出頭の理由はまったくの別件――家主への家賃滞納の件であった。拍子抜けするような安堵の瞬間、ラスコーリニコフは、再び自分の「逃げ切れるかもしれない」という希望を取り戻し、警官たちに対して、かすかな自信と横柄さすら見せ始めるのだった。
🧠 感想と考察
揺さぶられる精神、読者もまた揺さぶられる
第1篇までは、ラスコーリニコフの貧しさや孤独、そして殺人という大きな決断に至るまでが主な焦点でしたが、第2篇に入り、いよいよ「バレるかどうか」「どのようにバレるのか」という緊張のサスペンスが始まったと感じました。
物語の興味の中心が「内面の葛藤」から「社会との接触」へと移り、ラスコーリニコフの精神はますます不安定になっていきます。彼の恐怖、焦り、そして「白状してしまったほうが楽かもしれない」という心理には、非常にリアリティがありました。
実際、自分自身にも身に覚えがあります。小さな過ちであっても、「もう隠し通すのは無理だ」「いっそすべて話してしまいたい」と思ったことは何度もあります。そして、相手の反応を見て「まだバレてない」と確信したときの、あの胸をなでおろす瞬間。そうした感情が、この章のラスコーリニコフには強く表れていて、読んでいてとても共感できました。
殺人という重大な罪を犯した人物であるにもかかわらず、その後の彼の小心者ぶりには、人間的な弱さがあらわれており、だからこそ読者として感情移入しやすいのかもしれません。
🧍♂️【登場人物メモ】
| 名前 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| ロジオン・ロマーノヴィチ・ラスコーリニコフ | 本作の主人公。貧困に苦しむ元大学生で、老女とその妹リザヴェータを殺害した犯人。 | この章では犯行後の混乱と錯乱が描かれる。警察からの呼び出しに恐怖し、精神的に追い詰められる。 |
| ナスターシャ | ラスコーリニコフが間借りしている部屋の使用人。 | 食事を持ってきたり、警察からの呼び出しを伝えるなど、生活と外部世界をつなぐ存在。ラスコーリニコフを「かわいそう」と思い、世話を焼く。 |
| イリヤー・ペトローヴィチ | 警察署の副署長で、短気で高圧的な性格。 | この章での警察署のやり取りで登場。ラスコーリニコフに対して威圧的な態度をとるが、殺人とは関係ない用件での呼び出しだった。 |
| ニコジーム・フォミッチ | 警察署の署長 | イリヤーとは対照的に理性的で穏やか。警察内のやり取りにおいて、緊張をやや和らげる存在。 |
| ザルニーツィナ | ラスコーリニコフの住む家の家主。 | 家賃未納の件で訴え出た人物。今回はその関係での警察からの呼び出しだった。ラスコーリニコフは警察署でこの名を聞き、すべてが殺人の件ではなかったと安堵する。 |
| リザヴェータ(※故人) | 殺された質屋の妹。心優しい女性。 | 直接の登場はないが、彼女の死はラスコーリニコフの精神に大きな影響を与えている。 |
| アリョーナ・イワーノヴナ(※故人) | 質屋の老婆。ラスコーリニコフに殺害された。 | 本章では直接登場しないが、主人公の恐怖と罪悪感の中心にある人物。 |
📝 まとめ
この章では、「バレたと思ったが、バレていなかった」――そんなスリルと安堵が混在する心の動きが、非常にリアルに描かれていました。
作者ドストエフスキーは、ただ犯罪の顛末を描くだけでなく、犯人の「その後」に重点を置き、読者の心を巧みに揺さぶります。この不安定な精神状態がどこへ向かうのか、そして次は誰が彼に接近してくるのか、目が離せない展開です。
※この投稿は、ドストエフスキーの『罪と罰』をじっくり読みながら、感想や考察を記録していくシリーズの一部です。
これまでの感想一覧はこちら ▶️【シリーズ一覧リンク】
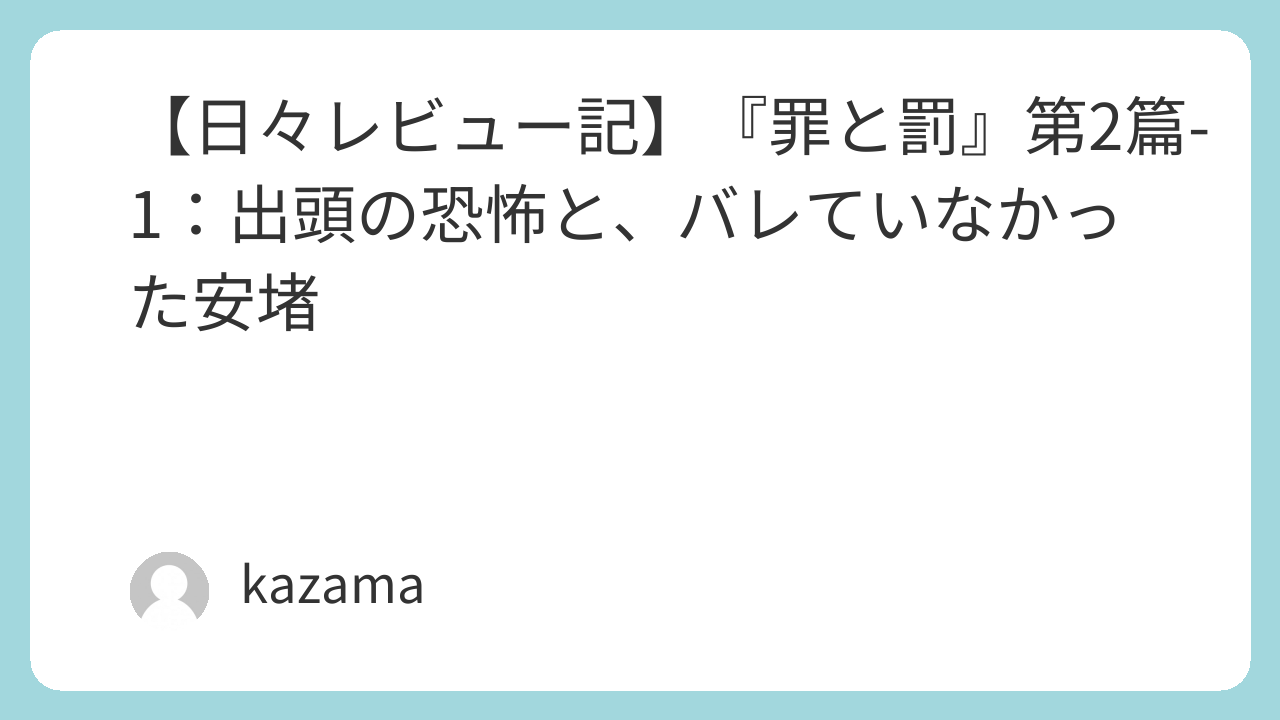


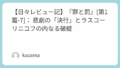
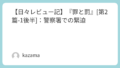
コメント