基本情報技術者試験の勉強をしていて学んだ「マルウェア対策ソフト(ワクチンソフト)」について、私なりにまとめてみます。
パソコンやスマホを使っていると、ウイルスやスパイウェアなどの“マルウェア”と呼ばれる悪いプログラムに感染することがあります。そんなとき、私たちを守ってくれるのが「マルウェア対策ソフト」です。
では、このソフトはどうやってマルウェアを見つけて、止めているのでしょうか?
マルウェアを見つける2つの方法
① パターンマッチング法
まず1つ目は「パターンマッチング法」。これは、マルウェアの特徴(シグネチャコードと呼ばれます)をあらかじめ登録しておいて、それと同じものを探すという方法です。
- メリット:一度登録すればすぐに検出できる。
- デメリット:新しいマルウェアは登録されるまで見つけられない。
だから、常にウイルス定義ファイルを最新にしておくことが大切です!
② 振舞い検知法(ふるまいけんちほう / ビヘイビア法)
2つ目は「振舞い検知法」。こちらは、プログラムの怪しい動き(ふるまい)を監視して、マルウェアかどうか判断する方法です。例:ファイルを勝手に書き換えたり、勝手に通信を始めたり。
- メリット:未知のマルウェアも見つけられることがある。
- デメリット:正しいソフトも誤検知するリスクがある。
この2つの方法を組み合わせて使うのが一般的です!
効果的なマルウェア対策のポイント
マルウェア対策ソフトを入れても、使い方を間違えると効果が落ちます。私が学んだ中で大事だと思ったポイントを3つご紹介します。
定期的にフルスキャンをしよう!
普段は「リアルタイムスキャン」で守ってくれますが、全部のファイルをチェックしているわけではありません。
だから、ときどき HDDやSSD全体を対象に「フルスキャン」を行いましょう。
バックアップも忘れずに!
どれだけ対策しても、完全に防げるとは限りません。
定期的なバックアップをしておくことで、もしものときにデータを守ることができます。
おわりに
基本情報技術者試験では、セキュリティの問題も多く出題されます。今回まとめたマルウェア対策の知識は、試験対策だけでなく、日々のパソコン生活でもとても役に立ちます。
実際に自分で「なぜフルスキャンが必要なのか?」や、「どうやってウイルスを見つけているのか?」を知ることで、セキュリティ意識がぐっと高まりました。
みなさんも、ぜひマルウェア対策ソフトを使いっぱなしにせず、「使いこなす」ことを意識してみてください!
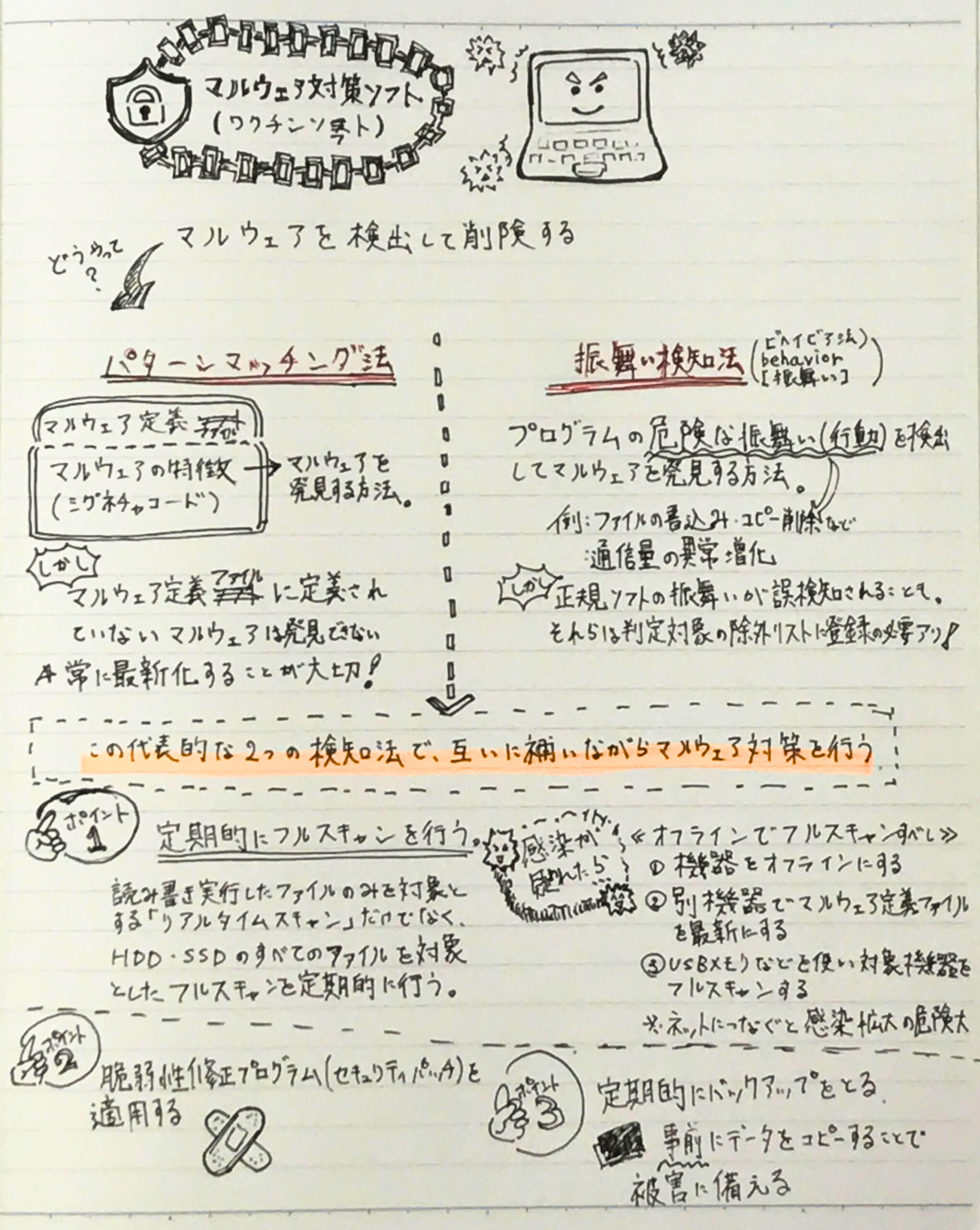


コメント